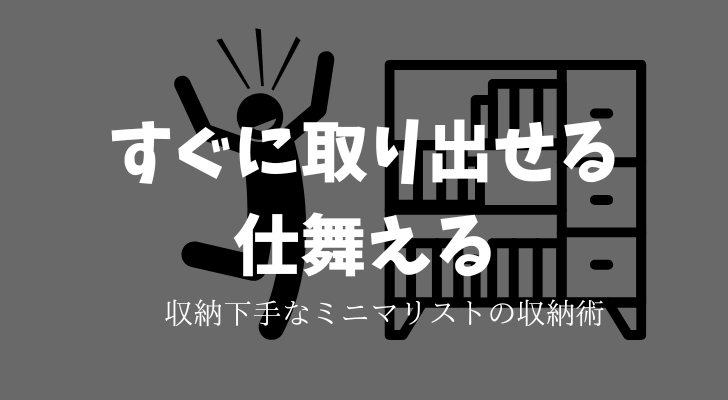- 収納が苦手で片づけられない

こんにちは、せい(@aodama_s)です。手仕事大好きアナログミニマリストです。
昔、部屋は収納ができていなくて物が散乱、ヒドイ有様でした。

使った物があちこちに散乱。
探すのに時間がかかる。
収納上手とされる人の収納術を見ても、なかなか真似できない。
収納ができなかったのは物が多すぎたから。そして、センスが無いから『綺麗な収納』なんて見た目が作れなかったんです。
だから物を捨てて、センスが無い自分を受け入れて、使う場所に使う物を置くだけというシンプルな収納にしたんです。
そうしたらすごく使いやすい収納になりました。もとに戻すのも簡単。使いやすさを追求して生まれた美を機能美といいますが、これも機能美なんじゃないかと思ってます(笑)
本記事では使いやすい収納のためにやったことを紹介します。
- 何を捨てたらいいのか
- 使う場所に使う物を置くとはどういうことか
何を捨てたらいいのか
まずは物を捨てました。物が多いと、収納がものすごく難しくなります。物が多いときの収納の大変さは以下の通り。
- 物が多すぎて置き場所がない
- 出したら置き場所に戻せない
だからまずは捨てること。捨てる基準としては、ざっくりとですが1年着ていない服・使っていない物を捨てました。
重要なのは、まだ着れる服・使える物だからといって残さないこと。服は着てこそ、物は使ってこそ役目を果たします。
使いやすい収納のために捨てる!と、覚悟を決めてがっぽり捨てました。
その他、具体的に何を捨てたらいいかは下に記事でまとめています。
まだ表示できる投稿がありません。
使う場所に使う物を置く
物を捨てたら、あとは使う場所に使う物を置きます。
例えば、ぼくはお風呂には掃除用具を吊るしています。

こうすれば掃除したいときにすぐに手に取れます。

使いたいときにすぐに手に取れるし、仕舞う場所がすぐそこだから戻しやすいです。
使用頻度が高い物は収納しないのもあり
使う物の中でも毎日必ず使う物であれば、収納しないという方法もあります。つまり、出しっぱなしにするということです。

毎回出したり戻すくらいなら、最初からそんな手間を無くしてしまえばいい。
収納された状態を維持するには、どれだけ手間を減らすかもポイントです。物を持って移動する距離はもちろん、引き出しから出す労力すら無くしたほうがいいです。

ほんのわずかな『面倒』と感じる心が、その辺にチョイ置きする要因になります。
ここまで収納の方法を解説しました。次からはおまけとして、収納するときにやめたほうがいいことを紹介しています。より使いやすい収納を目指したい人は読んでみてください。
やめたほうがいいこと

取り出しやすく、戻しやすい。そんな収納にするためやめたほうがいいことは以下の通りです。
- 重ねる
- 奥行きの長い収納容器
- 衣装ケースといった大型の収納容器
重ねる
書類や服などは重ならないようにしましょう。重ねると下の物が取り出しにくくなり、戻しにくくもなります。
自分が今何を持っているのかを把握しやすくため、可能な限り重ねないように。また、物だけでなく収納容器も重ねないほうがいいです。

重ねると下の容器に入れた物が取り出しにくくなってしまいます。収納の目的は使いやすくすること。使いにくくなるような置き方は避けたほうがいいです。
奥行きの長い収納容器
引き出しなど、奥行きの長い収納容器は避けましょう。特にそういった容器に小物を入れると、引き出しを全部引っ張り出さないと取り出せないほど奥に入り込むこともあります。
そうなると、入れた小物の存在を忘れてしまいやすい。無くしたと勘違いし、買い直してしまいます。

引き出しの奥に何本もペンが入り込んでしまい、無駄にペンを買い直していました。
衣装ケースといった大型の収納容器
衣装ケースなど、一抱えもあるような大型の収納容器も避けたほうがいいです。
人は空いている箇所があると埋めたくなるという習性があります。せっかく物を捨てようとしても、収納に空きがあると物を戻して空きを埋めたくなってしまう。

収納容器がみっしり埋まっていると、謎の達成感が生まれるので要注意です。
できるなら、収納容器は収納する物の量に合わせるといいです。物を捨てて空きスペースができた収納容器は一旦捨てて、収納する物の量に合わせた収納容器に買い直すことをオススメします。
ここまで収納のポイントを見てきました。次からは実際の収納をお見せします。
実際の収納状態
お見せする収納は居間と台所です。見てみたい方だけ、↓をクリックして広げてみてください。
居間
居間には棚と押入れ、突っ張りポールハンガー、そして収納スツールがあります。
棚

棚は一切収納していません。全てそのままです。この棚には毎日使う物など使用頻度が高いものを置いています。一々仕舞うのは手間なので、すぐ使えるようにこのようにしています。
ここには日記帳やノート、本、財布や車の鍵などを置いてます。一番下にはデスクトップパソコン。見える状態にすると、持ち出しやすく戻しやすいので、維持もしやすいです。
押入れ

この画像の範囲全てにぼくの持っている服が収まっています。中段には普段着る服を、上段の白いケースにはシーズンオフの服が入っています。
中段右の白い吊り下げボックスにはズボンやルームウェアを、シャツやタートルネックセーターなどはハンガーに下げてそのまま吊るしています。

黒い服ばかりで見づらいですが、複数の種類の服が掛けています。
ぼくは服はワンパターンしか持っていません。服の種類は圧倒的に少なく、また枚数も少ないため、これで収まっています。
体は一つしかないし、服は365日全部違う服を着なければならない決まりもありません。着ていない服はどんどん捨て、着ている服だけを掛けるクローゼットに仕上げましょう。
突っ張りポールハンガー

ここにはアウターや外に散歩するときのスウェットを掛けています。冬の時期ですと、手袋やニット帽も追加されます。
突っ張りポールハンガーは服を仮置きするのに便利なうえ、スペースを取らないのが特徴です。雨や雪などで濡れた服を乾かすのに掛けておくのにも有効。
ただし、あくまでもまた次着るための仮置き。もう洗濯する服や、シーズンオフの服をいつまでも掛けっ放しにすることはしません。
収納スツール

こちらは一時置き場として使っています。今捨てて大丈夫か?など迷った物や、区分けしたときに置き場所が決まらなかった物などを仮置きしておく場所。
今は皮製品手入れセットや裁縫セット、通帳やハンコが入っています。
台所
台所の収納派はメタルラックと、シンク下、コンロ下、シンク上の棚になります。
メタルラック
まず台所の外にはメタルラックを設置し、そこに物を置いています。

置いているのは水切りかごや、洗ったプラスチック容器、ティッシュです。どれも台所で使う物なので、すぐに手に取りやすいようにしています。
シンク下

こちらは食器や調味料、大きめの保存容器を置いています。
どれもそのままです。そのままでも置けるように、持ち物はできるだけ減らしています。
コンロ下
鍋はステンレス鍋とミルクパンが一つずつ。

ステンレス鍋はコンロの下の空きスペースに、ミルクパンは使用頻度が高いのでコンロの上に置きっぱなしです。
シンク上の棚
シンク上の棚には、身だしなみアイテムと工具類、消耗品の在庫を置いています。




台所に身だしなみアイテムを置くのは、今借りている部屋に洗面台が無いので、台所が実質洗面台になっているからです。工具類は使う場面が部屋全体ですが、使用頻度が低いので空きスペースとなっている棚に置いています。
ここまで収納について見てきました。ところで、

どうして私は収納が苦手なんだろう・・・
と考えたことはありませんか?他の人は出来てるのに、どうして自分は同じことができないのか。何が違うから自分はできないのか。
そこで次は、ぼく自身を省みて収納が苦手な理由を考察してみました。
収納がどうして苦手なのか
収納が苦手なのは、マルチタスクが苦手だからと考えました。つまり、シングルタスクが得意ということです。
綺麗な収納について分析すると、以下のことを同時に考える必要があります。
- 物の配置場所
- 全体から見たバランス
物を使いやすい場所に置いたとき、周囲からどのように見えるかを同時に考える。これがマルチタスクが苦手なぼくにはできないことでした。
なので、ぼくはシングルタスクで考えるようにしました。『使う物を使う場所に置く』と考えることを一つに絞ったんです。
シングルタスクで考えることで、収納ができるようになった。そのように考察しました。
最後に:物を減らせば収納は簡単になります
収納下手なミニマリストがやっている収納術を紹介しました。
収納してみて分かったのは物を減らすことの重要性でした。物を減らせれば、収納の8割は終わったも同然。是非使いやすい収納に挑戦してみてください。
本記事を読んでの疑問、実践してみたけどうまくいかなかった等あれば是非コメントで教えてください。可能な限り回答させていただきます。
この記事が役に立ったと感じたら、↓のボタンよりぼくのXのフォローをしていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします