こんにちは。
学生の皆さん、校則守ってますか?

と言ってしまいますと、「あんな校則守るわけがない」「なんで守らなくちゃいけないの?」「髪染めちゃいけないとか意味が分からない」等々そんな非難の声が飛んでいそうな気がします。
今回はそんな非難の声にお応えして、どうして校則を守らなくてはいけないのか?という疑問を持っている方々にその答えを私なりの考えで答えていきたいと思います。
Table of Contents
校則の中身に意味はない

はい、いきなりこれです。
校則の中身そのものに意味なんてありません。髪を染めるな?染めたところで何も変わりませんね。黒髪だから学力が向上する、金髪だから頭が悪い、そんな研究データ聞いたことがありません。
スカートの丈の長さを弄ったところで、「けしからん!」などと言いながら目を向けるスケベなおっさんの目が向かうだけです(それはそれで嫌でしょうが(笑))。
そもそも私自身、既に社会人として学校を卒業している身ですが、渡された生徒手帳を見て校則を確認した覚えがありません。叱られて、「そんなこと校則にあったんだ」程度です。
そのように、卒業してしまえばもう校則なんて何の役にも立ちません。そんな期間限定の校則の中身に意味があるのか?何の意味も無いんです。
重要なのは「校則を守る」こと

校則の中身に意味はありません。しかし、だからといって校則を守らなくていいというわけではないんです。大事なのは、校則を守ること自体に意味があるからです。どんな内容であったとしてもそれを守ること、それが社会人になったときに、生きやすい状況を作ることに繋がります。
次からは、逆に校則を守らないことがどうなるのかを具体的にお話ししていきます。
校則を守らないとどうなる?
校則を守らないと、いわゆる不良というレッテルを貼られます。

このレッテルを皆さんはどう見ますか?ルールに縛られずに格好いいですか?自由でいいなぁと思いますか?
私は、なんて生きづらそうなんだろうと見ます。
不良というレッテルを貼られると、まず教師に目を付けられますね。服装や髪型について逐一指摘を受けます。それを繰り返せば、今度は教師から家庭に連絡がいきます。そうなると今度は両親からも疎まれるようになってしまいます。
学校には五月蠅い教師、家には無視する親。そうなった不良には外しか行く場所がありません。しかし、深夜で外を出歩けば今度は警察が出てきて、補導されてしまいます。
こうしてただ書き連ねただけですが、これだけでもなんて息苦しいんでしょう。
しかし、これだけでは終わりません。そうしてルールに縛られないでいた不良も、一人でいることには耐えられなくなり、同じ不良を求めるようになります。そこで結局、最後にはルールに縛られることになるのです。

不良グループは、一見すると無法者のように見えて実態は完全な上下社会です。上の者には絶対に逆らってはいけない、がんじがらめのルールしかないわけです。校則なんて何の意味があるのか?そんな疑問を抱くことすら許されない絶対ルールが待ち受けていたんです。
そこで不良はついにルールを守ることになります。何故なら、そこでのルールを守らないという行為は追放されるか、私刑というという立派な罰があります。校則の罰なんて大した効果はありません。ですが、どこからも弾きだされ、それでも仲間を求めた不良の最後の場所。そこすら追い出されることだけは避けます。だから不良は、死に物狂いでルールを守ります。罰を受けないために。追放されないために。
ここまで、校則を守らなかった不良がどうなるのか?という観点でお話ししてきました。ルールを守らずにいたところで、最後にはルールを守らざるを得ない状況になります。ルールが無い環境は無く、ルールを守らずにいられる環境も無いのです。
ここで言えるのは、校則とはルールです。ルールの中身がなんであろうと守らなければ生きづらくなるということです。ルールの中身に疑問を思うのは自由です。ですが、守らなくてもいいということとは全くの別なのです。
ルールの中身を自己解釈する危険性
ここからは、ルールの中身を自己解釈してしまう危険性を説いていきます。
自己解釈してしまうとは、「このルールは守ったところで意味が無いのだから守ることは無い」とルールを自分の解釈で守らなくてもいいのだと判断し、守らない事を言います。
これは非常に危険です。一見すると、ちゃんとルールの中身を確認したうえで自分で判断しているんだから立派じゃないのか?と思われるかもしれません。何も考えずにただルールを守る人よりも、よっぽど考えていると思うでしょう。
考えるところまではいいです。ですが、だからといってそれを実践してしまうのは危険です。
例えば、Aさんは車を運転していたとします。ある道路は制限速度が30km/hでした。しかしその道は何度も通ったことがあり、事故を起こしたことがありません。時々、その制限速度を超える60km/hで走ったこともあります。でも、事故を起こしたことはありません。
そこでAさんはこう考えます。「この道は制限速度が30km/hだけど、60km/hで走っても事故を起こしたことはない。30km/hという制限は事故を起こさないようにするためだから、事故が起きないのなら大丈夫だ。だから60km/hで走っても問題はない」と。

この思考の流れ。これは、校則を守らなくてもよいと考える学生の思考と同じではありませんか?学校は勉学に励む場であり、言ってしまえばテストの点数され良ければいい。なら、テストの点数が低くなければ何をしても問題はない、ということと。
いや、それは校則だからで…という声も聞こえてきそうな気がします。校則は校則、法律は法律と。しかしそこに甘い罠が待ち受けているのです。
「思考の慣れ」という罠
人間には思考の慣れというものがあります。
例えば、ネガティブな人は物事を常にネガティブに考えます。しかしそれは生まれた瞬間からそうだったのでしょうか?生まれた瞬間、つまり赤ちゃんの頃からネガティブだった?そんなことはありませんね。成長していくうち、最初は特段大きい不安な出来事にネガティブな考えを持つようになっていった。そして、そう考えるうちに徐々に小さい出来事もネガティブに考えるようになっていき、結果的には常にネガティブに考えるようになります。
これが思考の慣れです。徐々にそう考えることに慣れ、その考える範囲を拡大していくのです。これを、自己解釈で考えるとどうなるでしょう?

もう一度不良の話に戻ります。前日まで普通の生徒が、翌日いきなり金髪・ピアスに変わるでしょうか?変わりませんね。不良は、最初はある一部だけを変えてきます。その変えたときの周囲の反応から、「これくらいなら大丈夫だ」と理解します。そして、次にまた変えてきます。その変えたことに対する周囲の反応から「これくらいなら大丈夫だ」と考えます。これをひたすら繰り返すと、最終的にはとんでもない変化となります。
このように自己解釈するという思考に慣れてしまうと、「このくらいなら大丈夫だ」のこのくらいがどんどん広がっていってしまうのです。例として述べた、制限速度30km/hを60km/hを走るようになるのも同じです。いきなり60㎞/hで走ることはありません。最初は35㎞/hくらいだったのです。それが徐々に上がっていき、終いには60㎞/hで走るようになるのです。
自己解釈に慣れた人の末路

では、実際として校則を守らなくてもよいという自己解釈に慣れた人はどうなってしまうでしょう?
これは改めて説明するまでもありませんね。前述した不良のよう…いえ、不良以上に生きづらくなるのです。
自己解釈に慣れた人の末路①明確な罰
社会人になると、様々なルールやマナーがあります。最も大きいものなら憲法、その下に様々な法律、民法、刑法、地方自治体の出す条例…社会人にはそれらを守る義務があります。
そして校則と違うのは、ルールを破れば明確な罰があります。そこに自己都合の解釈が出しゃばれる余地はありません。「○○だから大丈夫だ」そんな理由は意味がありません。
確かにルールとは、何かしらを守るために作られたのがほとんどです。道路交通法なら、事故が起きないように。それを守っているのなら、問題ないと考えてしまうでしょう。
しかしそれは、どんなルールも自己解釈でどうとでも解釈できる、自己解釈が通るなら誰も罰を受けないでいられるというリスクがあります。それこそ、殺人すら自己都合でいくらでも自分の行為を正当化できます。あいつには殺されるべき理由があった、私には殺すしかなかった、だから殺人は罪にならない…そんな自己都合がまかり通ってしまいかねないのです。
そんな自己都合は許されないのが法律です。自己都合でいくら語ろうとも、違法は違法であり、罰を受けなければなりません。それが社会です。

自己解釈に慣れた人の末路②人の輪からはじき出される
そして、ルールを守らず罰を受けた人のことを、周囲の人はどうするでしょうか?距離を取るようになるのです。人との関わりが薄れていくのです。
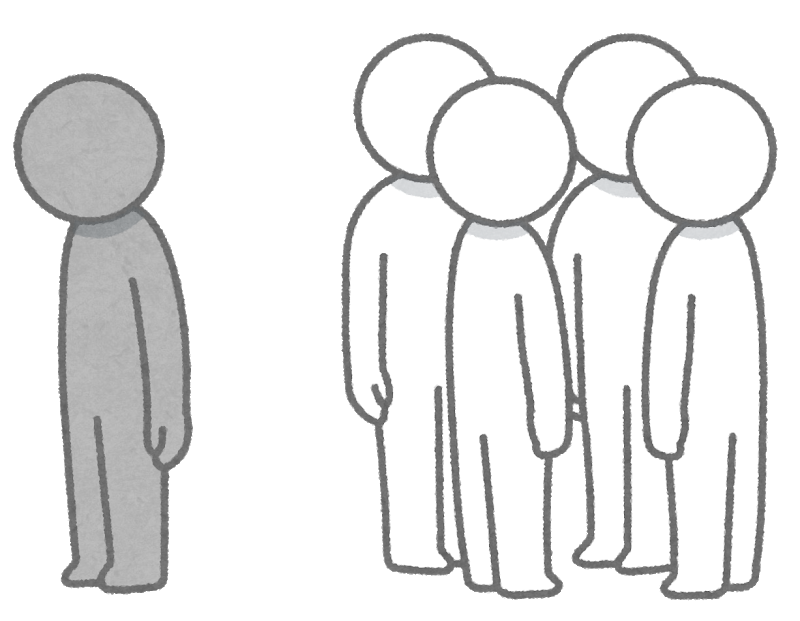
これは理屈で語るよりも、現実に周囲にそのような人がいたら?と考えてみれば早いでしょう。殺人をした者、放火をした者、誘拐をした者、強姦をした者、窃盗をした者…あなたはそのような人たちと関わり合いを持ちたいと思うでしょうか?刑務所から出所してきた人間と関わりたいでしょうか?
刑務所で服役してきたのなら、罪は清算されているはずです。しかし現実には一度罪を犯せば、清算されて普通の日常に戻れるということはありません。誰もそんな人間と関わりたいと思わないのです。
いや、そんな刑務所に入るような罪を犯せばそうなるでしょ?と思われる方、要注意です。そこまでのことをしなくても人は離れます。
あなたの周囲にはいませんか?言い訳ばかりで絶対に自分は悪くないと主張をする人が。自己解釈とは結局のところ、言い訳なのです。一切自分には非が無いと言い訳ばかりするような人と、あなたは関わりたいと思いますか?そこに答えがあります。
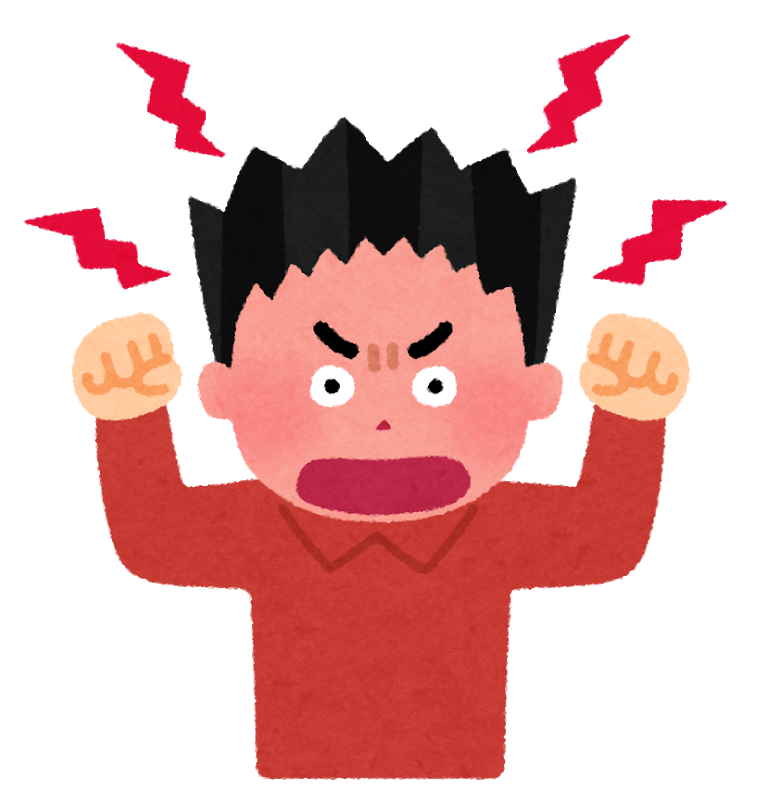
ルールを守れば生きやすい

ここまで、ルールを破れば生きづらいということについて語ってきました。その逆にルールを守ることは生きやすさに繋がります。
単純な話ですが、ルールを守って行動する人はそれだけで信頼されます。信頼できる人の周囲には人が集まります。
例えルールを守る人のことを、融通が利かない人、頭の堅い人と評される場合もあるでしょう。しかしだからといってそれは信頼が無いわけではありません。そのようにからかっても、その人の行動そのものには信頼があるのです。
人々に信頼されている状況であれば、何をするにも気が楽ですね。何か頼みごとがあったとしてもすんなり受け入れてもらえるでしょう。頼まれることもあるでしょう。しかしその頼み事も、あなたを信頼しているからこそ。信頼されていなければ、それは頼み事ではなく要求になりますから。
最後に
以上、校則とはルールを守る癖を付けるためのものという私の解釈を解説しました。
ルールを守って生きるということは、息苦しいという見方を持っていた人もいるかもしれません。
しかし私は、ルールを守らないことこそ息苦しいことになってしまうと考えています。ルールの内容がどうであるとかを考えることではありません。
社会はルールの塊です。しかも、その場その場に応じたルールがあります。そのルールの数は校則など比ではありません。そして、「知らなかった」では済まないのが社会です。
そんな社会で生きやすくなるためには、校則を守る意識が何よりも必要です。校則を守ることを心掛ければ、社会のルールを守るという意識も自然と成り立ちます。ルールを守るあなたを、周囲の人は受け入れてくれるでしょう。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。もし、この内容であなたの校則に対しての考え方に何か変化があれば幸いです。

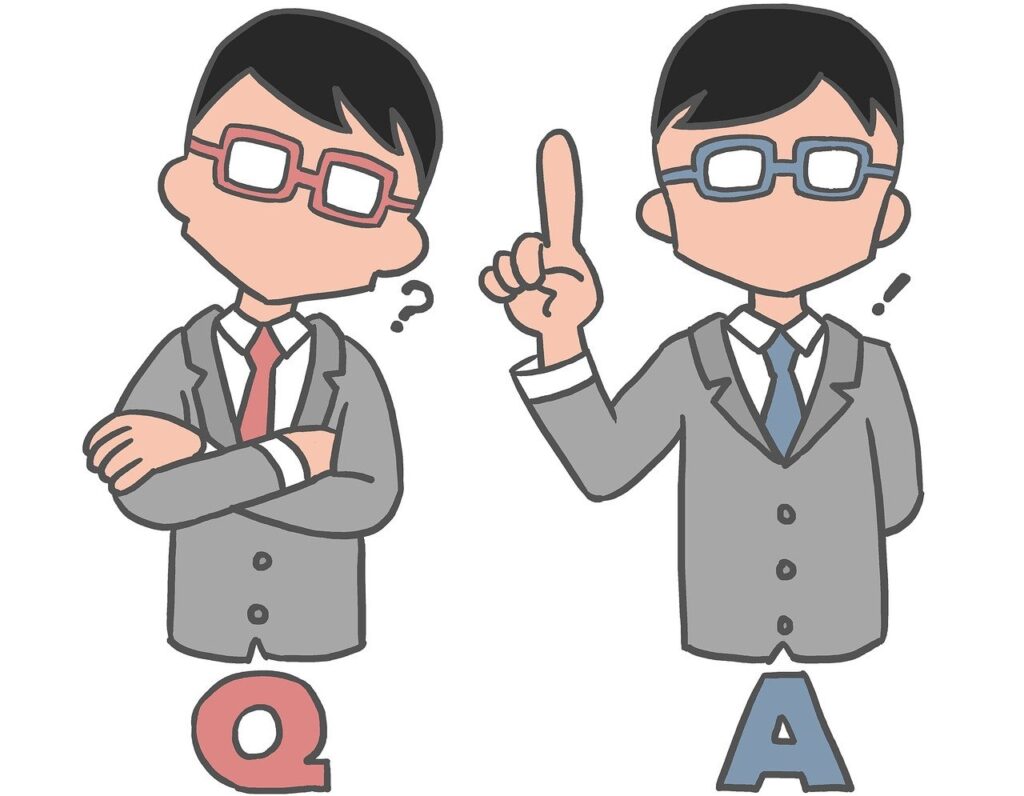


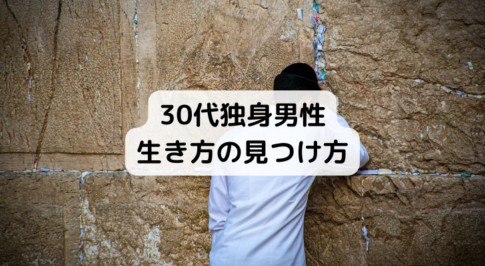


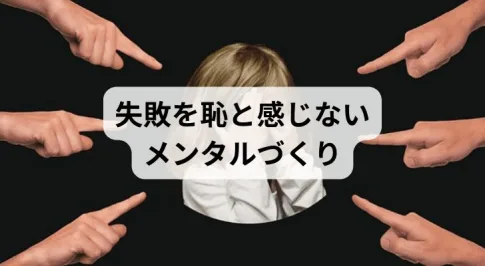
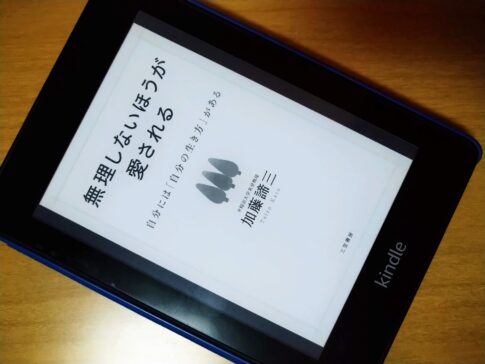








コメントを残す